|
陰々滅々とした話題が続いたので、今回は音の冗談の話を。
音の冗談と言っても、パロディのたぐい、聞こえる音自体が間抜けで笑えるものなどいろいろあって、それはそれで一章を費やして話ができるのだが、今回扱うのは、音名を使った文字遊びである。
まずは、音名について説明しておこう。
普通に使われる、
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ
という読み方は、主にフランスやイタリアを中心として使われている。この読み方の由来は、「聖ヨハネ讃歌」なる讃美歌の歌詞であるというのが定説である。
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mirages torum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Ioannes
各節の歌い出しの音が、順々に一音ずつ上がっているので、それぞれの音の名前として、この歌の各節の最初の発音を宛てたとされる。ただしこの歌には全部で6つしか音が使われておらず、シの音は出てこない。7番目の音に名前をつけなければならなくなった時に、最後の「Sancte
Ioannes」の各単語の頭文字であるSとIを用いて、Siとしたのである。
ただしこれには異説もあり、ドレミの音名はすでにこの歌より前に使われていて、この歌自体がそれに合わせて作られたのだと主張している学者もいる。そうだとすればこの歌もれっきとした冗談音楽と言えよう。
最初の「Ut」はイタリアでは発音しづらいので、「Do」に変更された。フランスでは語尾の子音を発音しないのが普通だから、今でも「Ut」のままである。
SolとかMiとかいう単純な音節によって音を表すということで、これによって歌うことをソルミゼイションsolmizationという。この単語もなんとなく冗談ぽい。日本語では階名唱法と訳されているが、ドレミ式というように訳した方が原語のニュアンスに近い。
音名唱法ではなく階名唱法としているのは、このドレミ式は、次に述べる英語流・ドイツ語流・日本語流と違って、固定した高さの音を表すとは限らないことがあるからである。ドイツ語や英語でC音、あるいは日本語でハ音と言えば、これはピアノの中央の音、あるいはそれからオクターブ移動した音であって、他の音を意味しない。しかしドというと、ハ長調であれば確かにC音やハ音と同じ音で問題はないが、これがト長調になると、G音やト音と同じ音と見なされる場合がある。つまり、調が変わった時に、実際の音の高さに関わりなく、その主音をドと呼ぶ──いわゆる移動ド唱法というのがかなり広範に普及しているのである。移動ドでは、ドレミというのは「音の名前」というよりは「音階を構成する名前」というべきなので、音名ではなく階名という別の呼び方をするわけである。
ドレミはこういう具合で少々ややこしいところがあるが、それを措くとすると、いちばん簡単に思いつくのは、音の高さに文字を対応させることであろう。音にABC……と名付ける方法は、おそらくドレミよりも早い時期に考えられたものと思われる。
ただし、このABCは、当時の教会旋法のひとつであるエオリア調に即してつけられてしまった。実はこれは、現在のイ短調に相当する旋法で、そのため最初の文字Aがドではなくラということになってしまった。結果として、現在少々学習者を混乱させることになっている。
ともあれ、このような対応になる。
|
|
|
|
ラ |
シ |
ド |
レ |
ミ |
ファ |
ソ |
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
これが英国やアメリカで使われている英語流の音名である。ポピュラー音楽のコードネームはこの英語流に準拠するのが普通だ。
ところが、日本の音楽教育ではドイツ語流が使われることが多い。
ドイツ語流もアルファベットを当てはめるのは同じだが、ただBが♭(フラット)のついたシを表す。フラット記号自体がアルファベットの小文字のbをもとにして作られた記号なので、そのためかもしれないが、ともあれ混同を避けるために、♭のつかないシをHで表すことにしている。
ここだけ見ると英語流の方が無理がなくて便利なようだが、実はドイツ語流には大きなメリットがあるのだった。
今まで、ピアノの白鍵に相当する音だけ考えてきたが、黒鍵まで考えると面倒なことになる。黒鍵、つまり半音の概念ができてきたのは、上記の「聖ヨハネ讃歌」などよりずっとあとのことなので、黒鍵の音にまで名前をつけることができなかったのだ。
やむを得ず、ド・シャープとかミ・フラットと呼ぶことになる。英語でも同様で、Fシャープ、Aフラットという読み方になる。
ところが、ドイツ語流では黒鍵の音も単音節で言えるのである。
シャープをつけた音は、もとのアルファベットに「is」をつける。フラットをつけた音は、「es」をつける。
ド・シャープはCis(ツィス)、ファ・シャープならFis(フィス)、ソ・フラットならGes(ゲス)という具合に簡単に言えるので、とても都合がよい。なおEesとなるべきミ・フラットはEsと縮められ、Aesとなりそうなラ・フラットもAsと呼んでいる。シ・フラットは伝統に従ってBである。このように多少の例外的な言い方はあるが、すべての音を単音節で言えるドイツ式は大変便利であり、どちらかというとフランス式の音楽教育メソードが主流になっている現在の日本でも、音名だけは依然としてドイツ式が普通に用いられているのである。
さらに、明治時代、日本でも音名をつけた。ABC……をそのままイロハ……に置き換えたのである。シャープは嬰、フラットは変と呼ぶことにした。現在これは調名(ハ長調、ロ短調など)以外にはあまり用いられていない。
以上、まとめるとこうなる。同じ欄にふたつ入っているのは、異名同音である。
フランス・
イタリア式 |
Do(Ut)
Si# |
Do#
Re♭ |
Re |
Re#
Mi♭ |
Mi
Fa♭ |
Fa
Mi# |
| 英国式 |
C
B# |
C#
D♭ |
D |
D#
E♭ |
E
F♭ |
F
E# |
| ドイツ式 |
C(ツェー)
His(ヒス) |
Cis(ツィス)
Des(デス) |
D(デー) |
Dis(ディス)
Es(エス) |
E(エー)
Fes(フェス) |
F(エフ)
Eis(エイス) |
| 日本式 |
ハ
嬰ロ |
嬰ハ
変ニ |
ニ |
嬰ニ
変ホ |
ホ
変ヘ |
ヘ
嬰ホ |
フランス・
イタリア式 |
Fa#
Sol♭ |
Sol |
Sol#
La♭ |
La |
La#
Si♭ |
Si
Do♭ |
| 英国式 |
F#
G♭ |
G |
G#
A♭ |
A |
A#
B♭ |
B
C♭ |
| ドイツ式 |
Fis(フィス)
Ges(ゲス) |
G(ゲー) |
Gis(ギス)
As(アス) |
A(アー) |
Ais(アイス)
B(ベー) |
H(ハー)
Ces(ツェス) |
| 日本式 |
嬰ヘ
変ト |
ト |
嬰ト
変イ |
イ |
嬰イ
変ロ |
ロ
変ハ |
さて、前提となる音名の説明だけでずいぶんかかってしまったが、ともあれ音に対してこういう言葉もしくは文字が割り当てられているということは、言葉や文字と音を対応させることができるということを意味している。
最初に気づいた人が誰であるかはわからないが、こういうジョークみたいなことを大まじめでやった最初の巨匠はバッハであった。
バッハの綴りはBACHであり、これはすべて上のドイツ式音名に含まれる文字である。バッハはもともと数秘術とかそういったことに興味があったらしいので、自分の名前が音に変換できることに気づいた時には天の啓示を受けたような気がしたことだろう。
もちろんバッハは、この音を作品に採り入れた。他にもあるかもしれないが、有名なのは最後の作品「フーガの技法」で、未完に終わった終曲の後半に、高らかに奏でられる。この曲には、その前に2つの主題が置かれて、これが組み合わされながら次第に高まってくるのだが、そのあとでバッハは高々と自分の名前を叫んだわけだ。これが第3の主題となって、クライマックスへと進んでゆく……はずだったのである。だが、結局バッハはこの長いフーガを完成させることはできなかった。
しかしこの「バッハ主題」──B・A・C・H──はその後いろいろな作曲家が「バッハへのオマージュ」として利用した。
シューマンもこうしたことが大好きだった作曲家で、バッハ主題による作品「バッハの名によるオルガンのためのフーガ」を、実に6曲も書いている(MIDIは第1曲)。
使われている文字が全部違うというところから、現代のセリー作曲家なども時々利用しているようだ。
何を隠そう、私自身も高校生の頃に書いた「無伴奏フルートのためのパルティータ」という曲でバッハ主題をかなり徹底して使わせていただいた。その中でいちばん露骨にわかる「シチリアーナ」の一部をMIDIにしてみたのでご笑覧あれ。
さて、シューマンが使ったのはバッハ主題だけではない。彼の処女作である「アベッグ変奏曲」からしてこの種のネタが仕組まれている。
アベッグというのは女性の名前で、ABEGGと綴る。言うまでもなく、これもすべて音名に含まれる文字である。これは友人の彼女の名前だったという話で、シューマンはこの名前が音で綴れることを喜び、早速そのテーマでピアノのための変奏曲を書いたのだった。この曲はポーリーヌ・ダベッグなるフランス名前の人物に献呈されたが、この人物は実在しなかったらしい。もちろんこの架空の人物の姓はd'Abeggと綴る。
次に綴りにこだわったのは『謝肉祭』である。これは20の小品からなる組曲だが、8曲目と9曲目の間に、「スフィンクス」と題された、番号のついていない謎のような楽譜がはさまれている。これがヒントだというわけだ。
実は『謝肉祭』はほぼ全曲を通し、アッシュASCHという街の名前が用いられているのだ。
英語音名にも、ドイツ語音名にも、Sという文字は出てきていないのだが、シューマンはこの地名を、3通りの方法で音に置き換えたのである。
まず、AとSを一緒に読んでドイツ語音名のAs(ラ♭)とする。すると、As−C−Hという音列が得られる。
次に、Sの発音をとる。「エス」であり、Es(ミ♭)と同じ発音だ。そこで、A−Es−C−Hという第二の音列が得られる。
さらにシューマンは、自分の名前SCHUMANNの中に、この4文字が全部含まれている(SCHUMANN)ことに着目した。それで、名前の中で4文字が現れる順番に並べ替え、S(Es)−C−H−Aという第三の音列を得た。
「スフィンクス」は、この3つの音列を並べたものである。そして、『謝肉祭』を構成する曲は、その大部分が、この3つの音列のどれか、もしくはいくつかを主要モティーフとして使っているのだ。バッハ主題だけで6曲も書いたことといい、シューマンという男はなかなか執拗である。
他にもいろんな作曲家が似たようなことをしているが、有名なのは、1909年にパリの音楽雑誌「国際音楽協会の音楽レビュー」が、ハイドンの歿後百周年を記念して、H−A−Y−D−Nというテーマに基づくピアノ小品を何人もの作曲家に依頼したケースがある。編集長のエコルシュヴィルが呈示したテーマは、シ−ラ−レ−レ−ソというものだった。
当時のフランス楽壇の最長老だったサンサーンスは、にべもなくこの依頼を断った。さらに後輩のフォーレにこんな手紙を書いている。
「YとNがどうしてレとソになるのか、誰か説明できるだろうか……君もこのようなばかげた試みには参加するべきでないと思う」
結局サンサーンスとフォーレは書かなかったが、もう少し若い世代の作曲家たちは面白がって参加したのだった。雑誌の依頼に応えて曲を書いたのは6人──ドビュッシー、デュカ、アーン、ダンディ、ラヴェル、ヴィドール──であった。このうちドビュッシー(「ハイドンを讃えて」)とラヴェル(「ハイドンの名によるメヌエット」)の作品は、いずれも2分ほどの小品ながら現在でも愛奏されている。
サンサーンスが解けなかったYとNだが、別に難しい暗号というわけではない。AからGまでは普通に音名通りに並べ、Hだけはドイツ式にシとする。フランスの雑誌がドイツ式を採り入れたのは珍しいが、ハイドンがドイツ系だから敬意を表したのだろう。さて、Gすなわちソの上のラで、もう一度Hを援用し、その上のシはI、ドはJ、という具合に単純に割り振っていけば、Nはソ、Yはレになることがすぐわかる。Hの使い方にちょっと無理があり、サンサーンスもそこに惑わされたのだろう。
こういう風にすれば、どんな名前でも音に対応させることができるわけである。エルガーの「エニグマ交響曲」も同様な仕掛けに基づいている。ちなみに「エニグマ」とは「謎」の意である。エルガーはこの曲に、音名対照によって親しい友人たちを多数登場させたのであった。
逆に、文学の側からのアプローチもある。アイザック・アシモフのショートミステリー「ユニオン・クラブ綺談」の中に「Mystery Tune(邦題「殺しのメロディー」)」というのが入っているが、殺されたバーのピアニストが、ダイイング・メッセージとしてあるメロディーを歌う。そのメロディーが犯人の名前を示しているわけだ。ミステリーなのでこれ以上は書けないが、ここまで読まれてきた皆さんにはほとんどバレバレであろう。
さて、日本では、上で説明した4種類の音名がすべて使われているので、応用範囲が拡がる。
「遙かな友に」の作曲者で、先年亡くなった磯部俶(いそべ・とし)さんは、サインを求められると一風変わったものを書いた。
お名前の文字で、まず「い」は日本式音名のイ、つまり「ラ」と読める。「そ」はそのまま「ソ」だ。「べ」はドイツ式の「B(ベー)」と考え、「シ♭」。「と」は再び日本式で「ソ」。「し」はそのまま「シ」……というわけで、こういう音符を書いてサインとしたのである。
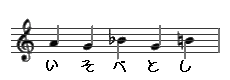
芥川也寸志さんが兵隊にとられていた時期に作ったと伝えられる「虱(しらみ)の歌」というのがある。ムソルグスキーの「蚤(のみ)の歌」に匹敵するほどのユーモラスな名曲と言われたが、なんのことはない、音符をただそのまま読めば歌詞になるという冗談音楽であった。
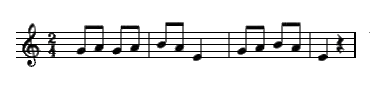
♪ソラソラ、シラミー、ソラ、シラミー♪
本当に芥川作品であったのかどうか、真相は定かではない。
私の大学時代、作曲科の講師として宍戸睦郎(ししど・むつお)先生がいらしていた。この苗字からして、なんだかむずむずするような気がするではないか。
丁度その頃、先生はかなり頭が薄くおなりであった。そこでついに、門下の学生が、こういうメロディーをモティーフにした作品を書いた。書いたばかりか、「ファゴットとピアノのためのスケルツォ」などというもっともらしいタイトルをつけて、その曲を学年末の作品演奏審査に提出したのであった。先生方には知らされていなかったが、学生仲間には「宍戸先生に捧げる曲」だという情報が周知されていたので、演奏審査の日、曲の半ば頃にこのモティーフが出てきた時には、一同笑いをこらえるのに苦労したのであった。さて、おわかりでしょうか? 前半は一目瞭然だと思うが、ポイントは後半である。答えは次項にて。
(2000.8.7.)
| 
